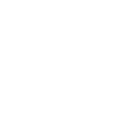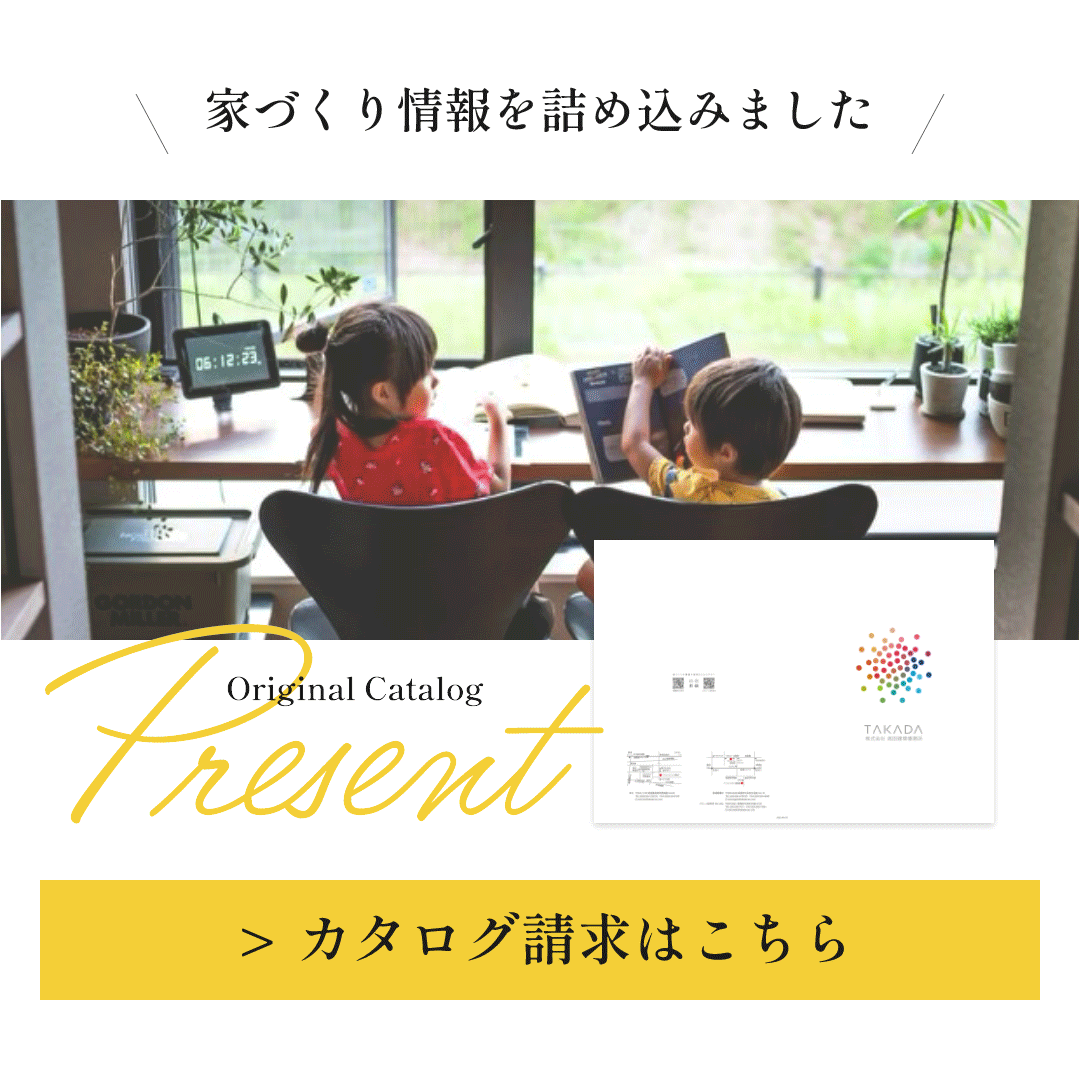まちづくりは、
間知づくり
「間知」と書いて「まち」と私たちは読んでいます。
景観は一棟一棟、具体的な建物が集まってつくられるものですが、
そのときにお隣との関係、間合いは居心地に大きな影響を与えます。
適度な“間”を“知”ることによって、快適な居場所をつくることができます。
「我が家の裏側は隣の正面」という言葉があるように、
間知づくりの視点を持てばお互いの距離感を大切にし、
心のよりどころになる風景ができるのではないでしょうか。
建築とはときに破壊をともなう行為だからこそ、
私たちは間知という見識を持ってまちづくりに取り組んでいます。
かわさきsix

「まちに緑を
つくって住む。」
緑に囲まれた遊歩道を中心に、6つの家族が緑と共に暮らす『かわさき six』長岡市川崎6丁目国道8号線に沿ってひろがる町。昔からの住まいが集まる住宅地。近隣には商業施設も多数あり、お買い物も充実。子育て世代におすすめです。6つの土地、全てが緑豊かな遊歩道に面しています。遊歩道に向けOpen道路からはClose程よい距離感が保てます。緑を近くに感じるお住まいで、穏やかな暮らしを始めてみませんか。

まち全体をコートハウスに
建物にはコートハウスという考え方があります。内部に中庭をつくり外からは見えないけれども、住んでいる方からするとのびのびと感じるつくりかたです。この考えをまちまで広げてしまうコンセプトです。
このまち自体が二面の道路に接するので、各お住まいの入り口の反対側はお互いの奥に面します。ここに緑の路地を取ることで、向かい合うお住まいの緩衝帯になり、さらに緑を近くに感じられるまちができました。

リプチの森

当敷地(1.6ha)は既存住宅地に挟まれたN自動車学校の跡地利用であり、その昔は田圃であった。太田川(自然に出来た川)と福島江(人工につくられた農業用水)に囲まれた土地でもある。環境破壊は近代化生産活動と同時に発生する負の資産である。町づくり・デベロッパーの効率一辺倒な町づくりの手法も効果としては環境破壊を助長してきた。町づくりをするに当たり、人々と自然が共生(関係矯正)して住まうために小さな一歩を踏み出すところから歩み始めることにした。人々の住まう居場所は、緑豊かな森づくりでもある。森・里・海の連環の中でつくられてきた、その土地の持つDNAの遺伝子の記憶を見直し過去から現在・そして未来へと再生される必要に迫られたプロジェクトでもある。当宅地分譲地を始めるにあたり「再び(リ)小さな(プチ)森をつくろう!」を合言葉に 「リプチの森」 と命名された町づくりは出発した。

人々と自然と歴史が共生し、
サスティナブルな
新しいまちづくり
現代は、インターネット仮想空間が肥大化している住環境にある。バーチャルの時代感覚が人間の感覚や関係を変えるとさえいわれる中で、みんなが集まって自分たちの手で緑の小さな森をつくるまちづくりが大切だと考える。人々と自然と歴史が共生し、サスティナブルな新しいまちづくりを目指した。
「再び(リ)小さな(プチ)森をつくろう!」を合言葉に「リプチの森」と命名されたまちづくりは、単に土地分譲をするのではなく思想を共有できる人々が集まる居場所をつくることをコンセプトにした。
1. 自然との共生
居心地の良いまちづくり=1/fの揺れをつくる。住民参加型のまちを育てる活動(植樹祭・夏祭り・ 野点のお茶会・光と雪のイルミネーション)
2. 歴史との共生
土地の持つ記憶をデザインサーベイし、新しいまちづくりにその記憶を埋め込みデザイン化する。
3. 人々の共生
老若男が混在するまちづくりを目指し、住民に開放する地域交流スペースを持つ地域密着型介護施設を併設する。
長岡市陽光台

巣舞づくりと間知づくりへ
「すまい」は私たちにとってとても大切な居場所です。 個々の家々が建ち並ぶ風景は、 その「まち」独特の風合いを醸し出してくれます。 個性ある「まち」が誕生しました。 長岡ニュータウン・12区画・陽光台プロジェクトです。 敷地は80坪から約100坪まで、住宅面積は40坪前後です。 「まち」を統一するための歩道やゲート、モニュメント塀が 当プロジェクトの風景を作り出してくれます。

個々の家々が持つ間合い(距離感)は、街としての顔を作ります。距離感を大切にしなければならないのは、人と人との関係だけではありません。家と家の間隔はとても重大です。適度な距離感がとても快・不快に影響するからです。その一つは視覚距離であり、また記憶の距離も大切に扱われなければなりません。 距離感と同時に大切なのが、家と家の「居方=向かい合い 方・並び方」です。至近距離でも方位をちょっと振ってやるだけで居心地の良さを確保でき、反対にどんなに遠くても双眼鏡で覗き込まれているような気分は良くないものです。「すま居方」は方向であり、「間知」は距離であります。この二つが上手く機能してくれることにより、より快適な住環境が作り出されます。「快適な居場所づくり」は方向と距離・大きさを持ったベクトルで表示されるものかもしれません。

かきの木通り

建築家の明確なヴィジョンが生きるまち
建築家の玉井一匡氏と共に、ふるさと早通で歴史を刻んできたレンガ塀や樹々を残し、自然と人間の共生をコンセプトにしたまちづくりを行いました。
集落の周りには見渡す限りの田んぼがひろがり、そのかなたには五頭連峰が連なる。私たちは、この土地の持つ性格を可能な限り残し、生かそうと考えました。それが気持ちのよい生活環境を生むからです。かきの木通りを通る道路は樹々のある広場をかわし、引き立てるように曲がりながら通り抜けます。家々の背後にも、それぞれの家を分かちながら結ぶための道も設けます。ひとりひとりの気持ちよいことが、同時にまわりの人々と環境にとっても気持ちよいことであるようなまちをつくり、これが、日本のまちをより良く変化させるようなモデルとなることを、私たちは目指しました。

「みちのかたち」と
「まちのかたち」
長い時間をかけて作られてきた「場所」の力と個性を生かし、まちの道路は3つの場所で曲がっています。
【両端】西側の町道、東側の県道、2つの道との接点は、ちいさな町の目印です。西側には、既存のアジサイの花や大きな樹木を生かし、東側には大きく育った柿の木2本を残して、その間を道が通り抜けるゲートにしました。
【公園と車回し】道路の3つの曲がり角にはふたつの広場とひとつの車回し。形のよい松とサクラのあるところを公園とし、これによって南側の区画はまちの仲間としてひとつに結ばれます。樹齢2-300年の高野槙は緑地として残し、住戸のため設けた南京櫨のロータリーは広場のような空間となります。
【遊歩道】ほとんどの敷地には遊歩道が接しています。それぞれの家の生活をたがいに結び、且つほどよい距離を保ちます。遊歩道は北の端で煉瓦塀を抜けて、早通小学校へ通う子供たちの通学路となるでしょう。

ミトロの森

私たちは常に「居場所さがしの旅」をしている存在です。
快適な居場所には、それが住まいであろうと都市であろうとひとつのベクトルが働いている。私たちがどちらを向いて立つかは、いかなる状況下でも重大な影響力を持つものです。同時に相対する関係においてはその距離感はとても大切です。方位と大きさはベクトルとして表示することができます。
すまいづくりもまちづくりも時間というステージの上で、ダイナミックにそして同時にスタティックに成長していくものです。時間というファクターは成長におけるキーワードである。成長するモデルはリニアー型、或るいは円形型その他さまざまである。
当間知づくりのモデルはもっとも原始的な宇宙の成長型をモデル化したもの、ビッグバーンである。ものすごいスピードとエネルギーを持って拡大膨張する形はまさに渦巻き型である。この渦巻きにはどこからでも膨張(成長)することができる仕組みが内臓されている。個々の惑星は既然態としてそのシステムを受け継いでもいる。どこにでも拡大膨張するエネルギーを持ち、どこででも立ち止まる力がある。
当間知プロジェクトは、6年で5診療所村として一度完成体を見たのであるが、再び成長する仕組みを持ち合わせているプロジェクトである。

ゾーニング

イメージ模型

渦巻型の成長モデル
みどりあふれる広場を核に、自然と人間の共生
宇宙が創られた時のような渦のコアをモデル化したものです。その渦のまわりに惑星があるように各診療所棟を配置してみました。それぞれの棟は、パーゴラ風ゲートからアプローチします。各診療所は自由な方向を向き、隣棟間は程よい距離をもっております。

外観パース

配置図

ロータリー
中央ケヤキの木はジャックと豆の木であり、鎮守の森のシンボルツリー 。ロ ータリーは宇宙のコア、ビッグバーンをイメージ し、各塔は惑星のように配置 される

パーゴラベンチ
RC壁は自然屋外ギャラリーとして、歩道を内部に取り込んで情報の交差点、ベンチは街の茶の間として孫からお年寄りまで、人々のよりどころでもある。

星整形外科医院

おがわ眼科クリニック

いぐち耳鼻咽喉科

貝瀬皮膚科医院

林俊壱クリニック 胃腸科・内科